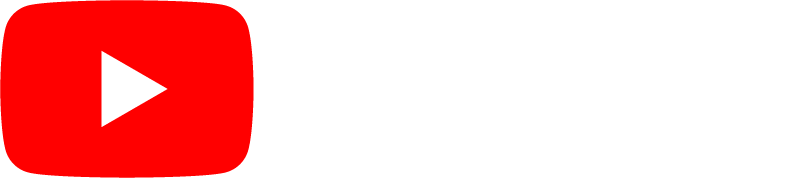スタッフ紹介
舞台ができるまで

脚本・台本(門馬 泰子)
「得意、不得意まぜ合わせ、よいあんばいにめでたしめでたし」という最後の講談師のせりふは、「個性をみがけば誰もが主役」というチ ャンチャンの信条に通じる。 劇のテ ーマは?と、 時々尋ねられるが、テーマは役者それぞれの個性である。どこも人手不足で余裕がない今、「めでたしめでたし」とはならず、偏りのある個性より、 バランスよく標準的に仕事をこなす力が求められる。 互いを認め合う場所で個性は花開く、とつくづく思う。
今年こそ早く台本を仕上げねば、と4月の沖縄公演を終え、 少しずつ温めてきた新しいお話をエンジンかけてまとめるべき夏に、 体調を崩して以来、 体が重だるく集中力がない。 時間ばかりかかって物事が前に進まない。 もともと遅れがちだった台本が今回、 記録を更新して、 全員に最終版を届けたのは11月である。 音楽、 衣装、 道具、 演出も、 急発進急展開、スピード仕上げで、 大迷惑をかけたが、さすが団員はじめ、スタッフ、保護者共々に、包容力があり誰も私を責めない。 いつも通りに、「あいよ!待ってました!」と受け止めると、 即エンジン全開でやるべきことを進めてくれる。
一生懸命だが不器用で、 ゆったりととぼけた雰囲気の、今回の主役をつとめるあんこちゃんの味を引き出すことができただろうか。 短い短い練習期間で本番にのぞむ役者たちに、心からのお詫びと、精いっぱいの演技に深く深く敬意を表したい。

道具(佐田 こずえ)
今年の道具担当は、大した仕事もせず本番を迎えることになった。過去に作ったたくさんの小道具の中から、今年使えそうな道具を見つけて、それらをリメイクしたのだ。リメイクしながら、その時頑張った自分を褒めてやりたい気持ちになった。同時に、こんな小道具もう作れないだろうなと、心が小さくつぶやく。小道具一つ一つに思い出があり、手に取ると、その道具を使った場面がよみがえり、団員たちの声が聞こえてくる。懐かしさと同時に団員たちの成長と自分の老いも感じる。(笑)それでも来年は頑張りたいと、前向きな気持ちでいる。

演出(神田 美栄子)
 毎年のことながらギリギリにならないと、踊りの振り付けや役者の動きや立ち位置が決まらない。踊りも何回か練習した後に納得がいかず急に変更してしまった。それでも意欲的に喜んで取り組む役者に心でそっと手を合わせる。
毎年のことながらギリギリにならないと、踊りの振り付けや役者の動きや立ち位置が決まらない。踊りも何回か練習した後に納得がいかず急に変更してしまった。それでも意欲的に喜んで取り組む役者に心でそっと手を合わせる。
自分の動きにキレがなくなったら踊りの指導もできなくなる?トレーニングは欠かさないようにと自問自答の日々。役に必要な小道具づくりは、要領よく早くなったのだが…。本番の役者たちのチーム力にかけるしかない!頑張れ!

音響(島田 かよ子)
 毎年悩ましいのが踊りなどに使う音楽の編集。多くの曲の長さが3分以上で、それでは長過ぎるから編集が必要なのだが、音楽を切ってつなぎ合わせるのが難しい。
毎年悩ましいのが踊りなどに使う音楽の編集。多くの曲の長さが3分以上で、それでは長過ぎるから編集が必要なのだが、音楽を切ってつなぎ合わせるのが難しい。
だから、曲の長さが程よくて、丸々1曲使える曲を見つけたときは嬉しい。そうでない曲のときは気が重くなる。何度やり直しても上手くいかない。
そもそも、音の切れ目ではないようなところで切ってつなぐから無理があるのだと思うが…何かいい方法を教えて欲しい。

舞台美術(背景画・ポスターの原画)
(藤尾 修二)
簡単な話の内容と登場人物を聞いて、まずは漠然とした情景を思い浮かべる。
その後、数日かけて登場する商店や役柄にまつわることを調べていると、イメージが次第に輪郭をともなって明瞭になってくる。霧が晴れてぴたっと焦点が合い、頭の中にくっきりと舞台の背景が見えたら、一気にえんぴつで下書きする。空想の羽根を自由に広げ、ここまでは楽しくスムーズにできるのだが、問題はこの後だ。年のせいか、目のせいか、下書きに細かく色をつけていく作業がつらい。
チャンチャンの舞台を見ると元気が出る、と舞台を見た人たちが言う。個性を輝かせたはつらつとした演技は、見る人の心を温かく元気にする。自分は絵を通して、そのはちきれそうなエネルギーや、ほのぼのとした温かさを伝えたいと思っている。彼らの素敵な一面が絵からもにじみ出るように…。そして、見る人の元気につなげたい。チャンチャンの絵を描くときは、いつもその願いをもって絵筆を握っている。















■ご紹介■•県展(岩田屋賞、ユネスコ賞、 奨励賞等) •日仏現代美術展(FBS賞) •谷尾美術展(特別奨励賞2回) 他

衣装 (奥 恵美子)
 衣装で役柄がわかるように、 役柄に合わせることが一番の苦労である。 それぞれの役柄がひと目で分かり、 その上で、 役者の個性と体形に合うように毎回工夫している。 その個性も体形も規格外の役者たち。だからこそ工夫も生まれる。
衣装で役柄がわかるように、 役柄に合わせることが一番の苦労である。 それぞれの役柄がひと目で分かり、 その上で、 役者の個性と体形に合うように毎回工夫している。 その個性も体形も規格外の役者たち。だからこそ工夫も生まれる。
あらすじや配役だけでは、まだ具体的なイメージがわかない。台本ができ、練習を見ながら考えをまとめて一気に仕上げる。というわけで、台本をもらったばかりの只今奮闘中、現在進行形である。
今回は、チャンチャンのお客様にいただいた着物を活用したい。和物の舞台は地味になりがちなので、ひと工夫いる。人形作家が本職の須﨑さんが、小物を調達したり豊富なアイデアも出してくれて、とても助かっている。
練習

 一昨年から、チャンチャン独自の健康チェック表を提出して練習に参加。壁ぎわの距離を保った椅子に座って静かに出番を待つ練習スタイルもすっかり定着した。全員マスクをしたまま、出番になると張り切って演技をする。緊急事態制限下の活動休止を挟んで、練習への意欲と集中力は増したように思う。音楽が徐々に増え、踊りや動きも増えると更に楽しく活気づく。
一昨年から、チャンチャン独自の健康チェック表を提出して練習に参加。壁ぎわの距離を保った椅子に座って静かに出番を待つ練習スタイルもすっかり定着した。全員マスクをしたまま、出番になると張り切って演技をする。緊急事態制限下の活動休止を挟んで、練習への意欲と集中力は増したように思う。音楽が徐々に増え、踊りや動きも増えると更に楽しく活気づく。
練習に遅れがちなスタッフに代わり、舞台担当の保護者3名(草野、石永、鶴崎)が、きっちりと道具の出し入れや役者の出番の誘導をしてくれて、本当に助かっている。11月になると、金曜夜の練習に加えて、それまで2部パフォーマンスの練習をしていた土曜の午前中にも劇の練習をする。単純なストーリーに奥行きを与えてくれるナレーションの喜多智子、舞台ソデのかなめ、佐藤裕子の大先輩二人が'カロわると、ぐっと練習もしまってくる。
応援団
●背景画作成
7月最後の土日、今年もスタッフ4名に力強い応援団7名が集まってくれた。藤尾修二氏の温かく楽しい原画が今回は3場面。合計ベニヤ板48枚分のパネルに忠実に拡大して描く。丸2日間、朝から夕方まで黙々と描き、腰痛と筋肉痛で翌日は悲鳴をあげることに
なる。パネルは、毎年新星社さんが21トラック2台で運んでくださる。新星社のお二人に、団員の兄の須崎凛之介さんも運搬を手伝ってくれて、スタッフの高齢女子?4名にはとてもありがたかった。
●本番
ドタバタのしろうと劇団を、何とかまとめてきちっと舞台で締めてくれるのが、20年来チャンチャンの定期公演をお願いしている山口市の「やの舞台美術」、舞台監督の河村高志さんと、照明の吉岡志乃さんである。いつもなら11月にスタッフが台本を持って打ち合わせに行く。しかし今回は、予定していた12月初旬の土日を延期したので、会場が空いていたのは28日の大ホール1日限り。前日の準備やリハーサルもできないため、短い時間で確実に舞台を作り上げなければいけない。場面ごとの雰囲気や役者の動きを確認したいと、金曜夜の練習を見学しに、山口から二人で来てくれた。
舞台準備から本番、片付けまで、舞台の裏をとりしきる。さすがプロである。
そして、受付けや会場整理、搬出入のトラック手配、舞台以外の様々な仕事を保護者が見事な連携プレーでやってのける。各地の公演でも同じだ。最近ますます洗練されて、毎回同じミスを繰り返すスタッフは、保護者の動きを仰ぎ見ている。
本番が無事(?)に終了すると、オヤジーズ&ブラザーズの出番である。大道具の解体と撤収から搬出作業まで、大活躍してくれる。